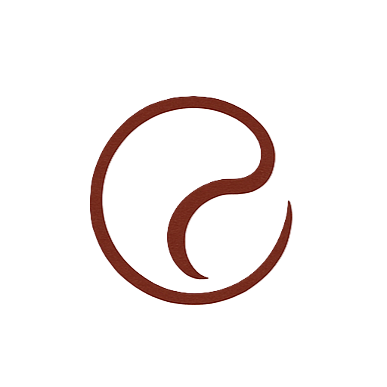インセンス カタログ
⒈ 独自にブレンドした”スパイス”の香り
スパイスインセンスは、東京・浅草の老舗香工房とともに、一から調香した完全オリジナル。
香りの設計はもちろん、一本一本の成形まで、すべて職人の手で仕上げています。使用するのは、天然由来の香料のみ。合成香料は極力用いずに、日々の呼吸に寄り添う安心とやさしさを第一に考えました。
–上質なインセンスへのこだわり–
温故知新 香りの雑貨屋のインセンスは、天然由来の香料をふんだんに使用し、一つひとつ丁寧に作り上げられた品です。
例えば、製造工程のなかでも特に重要とされる「生付け(なまづけ)」と呼ばれる作業。これは、練り上げたお香の生地を棒状に整え、木の板の上に均等かつまっすぐに並べていく繊細な技。わずかな力加減、湿度・温度の変化にも左右されるため、熟練した職人の感覚と技術が欠かせません。
職人の技と上質な素材から生まれたインセンス、その香りは焚いた瞬間から部屋に広がり、空気と調和しながら静かに深まっていきます。立ち昇る煙は、呼吸を深め、脳波をととのえ、心をそっとゆるめてくれます。どうか、呼吸が楽になり、安心感と心地よさに包まれるようなひとときを。香りを“纏う”ように暮らしに取り入れていただけたら幸いです。
–なぜ、インセンスなのか–
僕は、小さい頃から体が強い方ではありませんでした。特に気管支が弱く、季節の変わり目にはよく咳き込み、小児科に通う日々を過ごしていました。その病院では、漢方薬を処方してくれていました。漢方独特の、どこか苦く、深い香り。子どもながらに、あの香りが身体にしみこんで、少しずつ良くなっていく気がしていたのを、今でも覚えています。
そんな僕の実家は、葬儀屋でした。いつも線香の香りが漂っていて、それが当たり前の日常でもありました。けれどある日、ふと思ったのです。
「どうして、ある線香は咳き込むほどきつい香りで、ある線香は落ち着くんだろう?」不思議に思って、お坊さんに尋ねてみました。
その答えはとてもシンプルでした。——「咳き込む線香は、化学香料を使った中国製の安価なもの。咳き込まないものは、自然素材でつくられた日本の線香だよ。」そのとき、僕は初めて“香りにも質がある”ことを知りました。年月が経ち、大人になった僕は、あらためて香りと向き合う機会に出会いました。それが「インセンス」──つまり、香りを楽しむためのお香でした。仏壇に供える“線香”ではなく、自分の心と暮らしに寄り添う“香り”。焚いた瞬間、ふわりと広がる天然香のぬくもり。鼻先ではなく、心の奥で「気持ちいい」と感じる感覚。温故知新 香りの雑貨屋では、いまの自分が必要としている“心を整える時間”をつなぐような、そんなインセンスを取り扱います。
日本には、香道というすばらしい香りの文化があるのに、現代の暮らしの中で、香りを“味わう習慣”は少し遠くなってしまいました。だからこそ、香りを楽しむという文化を、もう一度、日常のなかへ。香りは、過去を癒し、今をととのえ、未来の自分をつくるチカラになると誰よりも信じて。
2. 抹茶の香り COMING SOON